災害時の備蓄について
なぜ、家庭での備蓄が必要なのか!?
市では避難所で最低限必要となる食料品や生活必需品の備蓄を行っていますが、大規模災害の混乱の中では備蓄物資がすぐに配分できるとは限りません。また、常備薬など特定の個人に対応した備蓄を行っておりません。
平成23年3月に発生した東日本大震災では、物流の混乱等により、満足に食料を調達できたのが発災後3日目以降という地域があり、電気の復旧に1週間以上、水道の復旧に10日以上の時間を要した地域もありました。
さらに、本市は南海トラフ地震が発生した場合、震度6弱以上が想定される「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。
このようなことから、各家庭においても災害等の非常事態に備え、最低3日分、できれば7日分の食糧・物資を備蓄することが重要になります。
特に食物アレルギー疾患のある方は、ご家庭での備えを確実に行いましょう。
家庭での備蓄方法について
家庭内で備蓄品について話し合い、下記リンク先のマニュアル等を参考に、食料品や水(1人1日3リットル)、照明器具、ラジオ等の情報収集機材のほか、各家庭や個人の実情に合わせ常備薬等の必需品を用意し、定期的に点検・交換を行い、いつでも持ち出しができるようにしておきましょう。
また、災害時は、特にビタミン、ミネラルなどの微量栄養素、食物繊維が不足し、体調を崩し風邪や便秘になりやすくなります。そのため、野菜ジュース等、野菜や果物の加工品も備蓄しましょう。
参考:「災害時に備えた食品ストックガイド」(農林水産省サイトへリンク)

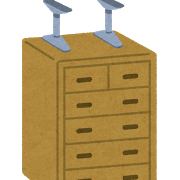

非常持出品と備蓄品リスト
下表は、非常持出品と備蓄品の一例です。
| 非常持出品 | 備 蓄 品 | |
|
一 般 的 な 持 出 品 |
飲料水 | 飲料水(1人あたり1日3ℓ) |
| 食料(1人あたり3食×3日分) | レトルト食品・アルファ化米 | |
| 財布(現金) | 給水袋(ポリタンク) | |
| 預金通帳・キャッシュカード | カセットコンロ(カセットボンベ込み) | |
| 健康保険証 | ティッシュ | |
| 顔写真入り身分証明書(運転免許証等) | ウェットティッシュ | |
| 懐中電灯 | 紙皿・紙コップ | |
| 携帯ラジオ | ラップ | |
| 乾電池 | 簡易トイレ | |
| 毛布、タオルケット | 水のいらないシャンプー | |
| 歯ブラシ | ビニール袋 | |
| ナイフ・缶切り | ランタン | |
| 衣類(着替え) | 長靴 | |
| 軍手 | 発電機 | |
| 上履き(スリッパ) | ||
| 常備薬 | ||
| お薬手帳 | ||
| 携帯電話 | ||
| 携帯電話充電器(モバイルバッテリー等) | ||
| 粉ミルク・哺乳瓶 | ||
|
感 染 予 防 物 品 |
マスク(サージカルマスク) | |
| 石けん | ||
| 消毒液 | ||
| 体温計 | ||
| タオル・ハンカチ | ||
| 使い捨て手袋(ビニール手袋) | ||
| ティッシュ | ||
| ウエットティッシュ | ||
| テント(自立式・ドーム型) |
こんなものも用意しておきましょう!
乳幼児のいる家庭
粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン、オムツ、清浄綿、だっこひも、バスタオルなど
妊産婦のいる家庭
脱脂綿、ガーゼ、さらし、T字帯、清浄綿、新生児用品、ティッシュ、ビニール風呂敷、母子健康手帳
お年寄りや障害者のいる家庭
着替え、オムツ、ティッシュ、障害者手帳、補助具の予備、常備薬、予備のメガネ、緊急時の連絡先
家庭の減災対策12項目
日ごろから防災・減災を意識するため、次の12項目を参考に、家庭でできる減災対策を心がけましょう。
| 減災対策項目 | 対策の内容 | |
| 1 | 建物耐震化 | 震度7規模(激震)に耐えられる建物倒壊防止の対策 |
| 2 | 避難経路確保 | 屋内外の避難経路と安全性の確保 |
| 3 | 頭部・足元保護 | 急な揺れで、頭と足にケガをしない対策 |
| 4 | 暗闇対策 | 夜間停電時のケガを防ぎ、安全に避難できる対策 |
| 5 | 家具類転倒移動落下防止 | 家具類・電気器具等の転倒、落下、移動を防ぐ対策 |
| 6 | ガラスの飛散防止 | 窓ガラスや食器棚等にフィルムを貼る飛散防止対策 |
| 7 | 緊急時持ち出し品の整備 | 避難経路、倉庫、車のトランク等への分散管理 |
| 8 | 備蓄品の充実 | 飲料水や食料等、生命維持のための家庭内備蓄 |
| 9 | 携帯電話や笛の必携 | 連絡や情報収集するためのモバイル通信機や笛の必携 |
| 10 | 衛生対策 | ウイルス感染症予防対策や凝固剤使用の排泄物衛生対策 |
| 11 | 救命知識の習得 | AEDの使用方法や骨折、捻挫などの応急措置の知識の習得 |
| 12 | 家族で話し合い | 家庭内の初動規程や緊急時連絡方法等の決定 |
ローリングストック法
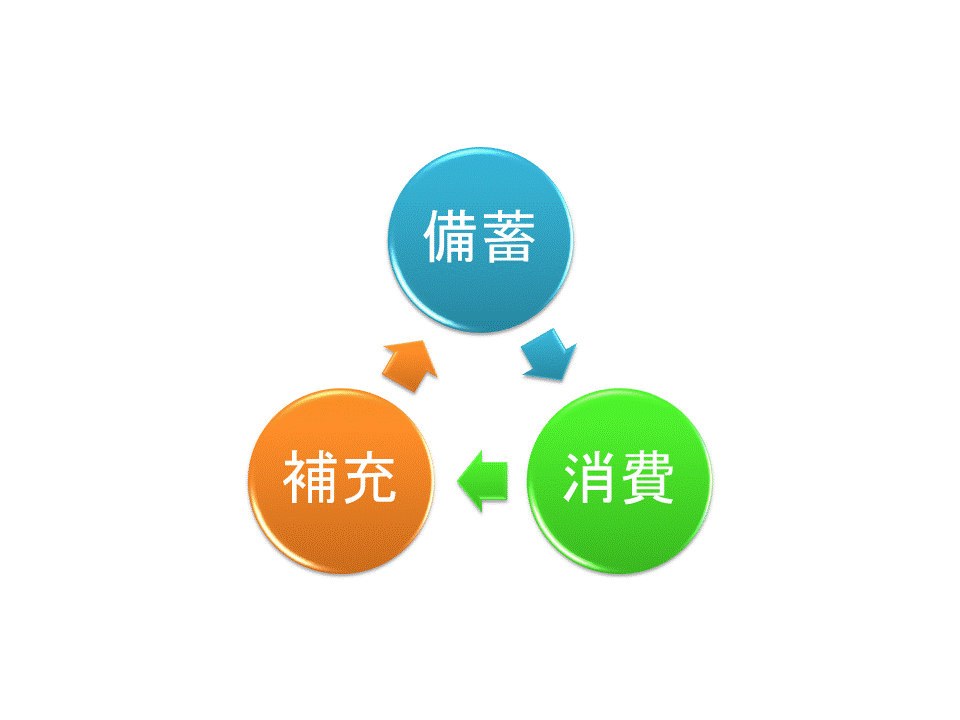
ローリングストック法は、家庭で備蓄している食料や水、カセットコンロのボンベ等を普段から定期的に消費しながら、消費した分を買い足す方法です。
備蓄食料に、普段愛用しているレトルト食品やインスタント食品を充当すれば、無理なく利用、補充ができます。
韮崎市の防災備蓄倉庫の現況について
本市では、地震等の大規模災害に備え、各小中学校・高校、各町の公民館や屋内運動場など全ての指定避難所に加え、市民交流センターや市役所へ備蓄倉庫を設け、食料や毛布、組立式トイレ、感染症対策用品など最低限必要になる物資を備蓄しています。
本市における各備蓄倉庫の現況は下記のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9368
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2025年01月06日